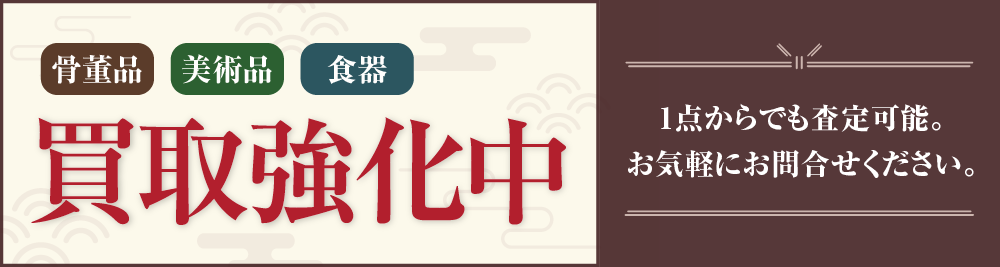【賤ヶ岳の七本槍】とは?7人の若武者についてご紹介します!
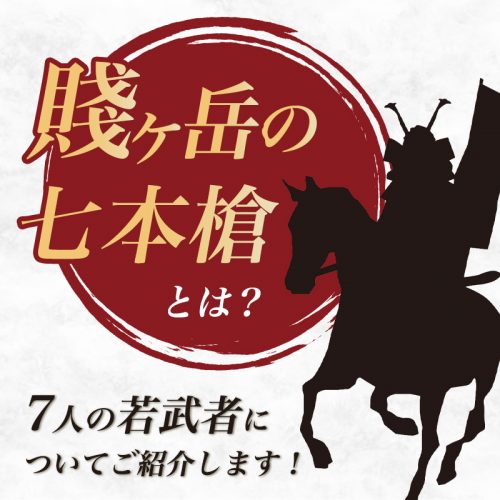
読まれています
今回の日晃堂コラムでは、刀剣の世界で有名な「賤ヶ岳の七本槍」についてご紹介します。
「七本槍」という名前が付いていますが、槍のことを指しているわけではありません。
賤ヶ岳の七本槍とは、「賤ヶ岳の戦い」で功名をあげた7人の若武者のことをいいます。
詳しくは当コラムでご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
賤ヶ岳の七本槍(しずがたけのしちほんやり)とは?
「賤ヶ岳の七本槍」とは、「しずがたけのしちほんやり」と読み、「賤ヶ岳の戦い」において功名をあげた「七人の若武者」のことを指します。
「賤ヶ岳の戦い」は1583年(天正11年)に賤ヶ岳(滋賀県長浜市)付近で起きた、「羽柴秀吉」と「柴田勝家」の戦いで、その後の日本の歴史を変える大きな転機となった戦です。この戦に勝利した豊臣秀吉が、「本能寺の変」で亡くなった織田信長がそれまでに築き上げた権力や体制などを継承。天下人への第一歩が開かれる、大きなきっかけとなりました。
この大切な合戦で功名を立て、賤ヶ岳の戦い後に豊臣秀吉から称えられた七人の若武者たちのことを、「賤ヶ岳の七本槍」と呼んでいます。功名をあげた”七人”というのは、ただの語呂合わせで実は九人いたという説や、昔から「七本槍」が虚名に近いという認識があった等、「賤ヶ岳の七本槍」については諸説あるのも事実です。
しかし、一般的に「七本槍」といわれた七人の武将の名が、「賤ヶ岳の七本槍」として広く定着しています。
刀剣買取なら、日晃堂にお任せください。
日本刀は100万円超える価値も多く、芸術品としても価値は高くなります。刀剣であれば刀、太刀、槍、薙刀、軍刀太刀、拵えなど品物を問わず、お持ちの刀剣を目利き致します。日晃堂の刀剣買取は全国対応、出張査定も無料ですので、ぜひご利用下さい。
【賤ヶ岳の七本槍】の武将たち
「賤ヶ岳の戦い」で勇猛果敢な働きをみせた七人の武将達。
実は「七本槍」には、「石河兵助」と「桜井佐吉」を加えた九人の武将がいたという説もあります。
ここからは、「賤ヶ岳の七本槍」と言われ広く定着している、加藤清正、福島正則、加藤嘉明、平野長泰、脇坂安治、糟屋武則、片桐且元、七人の武将についてご紹介します。
加藤清正(かとうきよまさ)
「賤ヶ岳の七本槍」七将の一人、「加藤清正」は安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将・大名です。
尾張国愛知郡中村(現在の愛知県名古屋市中村区)にて、1562年(永禄5年)6月24日に生まれ、1611年(慶長十六年)の同日に死去。”生まれた日と亡くなった日が同じ“という、珍しいエピソードがある人物です。通称で虎之助(とらのすけ)とも呼ばれています。
加藤清正が生まれた場所は豊臣秀吉の出生地にとても近い場所にあったこともあり、幼少の頃より秀吉に仕えていました。 加藤清正が12歳ぐらいの頃から我が子同然に育てられていたため、豊臣秀吉の子飼いの家臣だったことで特に有名ですね。豊臣秀吉に従って各地を転戦しますが、その見事な戦いぶりが認められ、肥後北半国の大名となります。
豊臣秀吉の没後に起きた関ヶ原の戦いでは、豊臣秀吉の側近だった「石田三成」率いる西軍ではなく、「徳川家康」率いる東軍に加勢。これは秀吉が残した幼子、「豊臣秀頼」を守る権力を蓄えるため、戦略的に軍力が上だった、徳川家康が率いる東軍に近づいたとされています。
関ヶ原の戦いで天下を獲った徳川家康から、肥後国一国と豊後国の一部を与えられ、加藤清正は熊本藩主になりました。そういった縁もあり、加藤清正は熊本などで「清正公さん(せいしょうこうさん)」と呼ばれ、現在でも親しまれています。
福島正則(ふくしままさのり)
「賤ヶ岳の七本槍」七将の一人、「福島正則」は安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将・大名です。
幼少時は「市松」と呼ばれていました。 尾張国海東郡(現在の愛知県あま市)で1561年(永禄4年)に生まれ、1624年(寛永元年)に死去。 福島正則の実家は武士ではなく、桶屋だったという伝話も残されています。
母が豊臣秀吉の叔母(大政所の姉妹)という縁があったため、幼少期より従兄弟の関係にあたる豊臣秀吉に仕えていました。同じく豊臣秀吉の親戚で、1歳年下の加藤清正と共に、豊臣秀吉に可愛がって育てられた人物として有名です。血縁関係にあたる福島正則と加藤清正は、豊臣秀吉にとっては信用のおかけるかけがえのない存在でした。
福島正則にとっても、加藤清正は盟友と呼べる存在で、二人で豊臣秀吉の身の回りの雑用などを行う「小姓」として豊臣秀吉に仕えました。
関ヶ原の戦いでは、加藤清正らと共に険悪の仲だった西軍「石田三成」を襲撃。
この事件がきっかけで、東軍「徳川家康」の昵懇大名の一人となります。
福島正則はその後、広島で大名となりました。「秀吉の一番槍」とも言われた猛将として、今でも広く知られる人物です。
加藤嘉明(かとうよしあき)
「賤ヶ岳の七本槍」七将の一人、「加藤嘉明」は安土桃山時代から江戸時代にかけて活躍した武将・大名です。
通称で「孫六」や「左馬助」と呼ばれていました。 三河国幡豆郡永良郷(現在の愛知県西尾市)で、松平家康の家臣「加藤教明」の長男として、1563年(永禄6年)に生まれ、1631年(寛永8年)に死去。七本槍の中では、一番最後に亡くなった人物です。
父は加藤嘉明が6歳の時、美濃国(現在の岐阜県南部)で死去。幼少期は馬喰(馬の売買をする人)に養われていたと伝えられています。馬喰時代に織田信長に仕える加藤景泰(光泰の父)に出会ったのを機に、豊臣秀吉に推挙されました。
豊臣秀吉は加藤嘉明を養子「羽柴秀勝」の小姓として仕えさせましたが、兵庫県南西部にある播磨三木城攻めにおいて、加藤嘉明は羽柴秀勝に無断で従軍。これが秀勝の養母「おねの方」に発覚し激怒されますが、豊臣秀吉はおねの方とは逆に、加藤嘉明の意欲を高く評価。関ヶ原の戦いでは、徳川家康率いる東軍に属し、西軍の石田三成を撃破することに貢献しました。
関ヶ原の戦いの後、大名となった加藤嘉明は数々の武功をあげ、その名を轟かせることに成功しました。
平野長泰(ひらのながやす)
「賤ヶ岳の七本槍」七将の一人、「平野長泰」は安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活躍した武将・旗本です。
平野長泰は七本槍の中で唯一、大名になれませんでした。尾張国津島(現在の愛知県西半部)で、平野長治の三男として1559年(永禄2年)に誕生し、1628年(寛永5年)に死去。 通称は「権平」で、当初は別名で「長勝」とも呼ばれていた人物です。
平野長泰は豊臣秀吉と同じ尾張国の出身ということもあり、若くして秀吉に仕えていました。平野長泰の名を一躍有名にしたのが、「賤ヶ岳の戦い」です。織田信長の死後、その後継をかけて豊臣秀吉と柴田勝家が争った「賤ヶ岳の戦い」ですが、この戦いで功名を上げた武将七人のうちの一人が平野長泰です。
豊臣秀吉の天下取りの立役者となった後も、秀吉の戦に参加を続けた平野長泰は豊臣姓を賜るなど、一定の評価をされるものの、大名になれないままその生涯を終えました。
豊臣方に味方するために、他の武将と同じく「関ヶ原の戦い」や「大坂の陣」で徳川家に仕えた平野長泰。その生涯を振り返ると、豊臣秀吉に忠実に尽くした人生を過ごした人物の一人として有名ですね。
脇坂安治(わきざかやすはる)
「賤ヶ岳の七本槍」七将の一人、「脇坂安治」は安土桃山時代から江戸時代にかけて活躍した武将・大名です。
脇坂安治は近江国浅井群脇坂村(現在の滋賀県長浜市小谷丁野町)で、脇坂安明の長男として1554年(天文23年)に誕生し、1626年(寛永3年)に死去。賤ヶ岳の七本槍の中では、「最年長の武将」です。通称で「甚内」と呼ばれ、和歌をたしなむ教養人としても知られています。
明智光秀の与力として、「黒井城の戦い」などで功を立てた脇坂安治は、自ら頼み込んで豊臣秀吉の家臣となります。その後、豊臣秀吉の諸戦に従軍して功を重ねた脇坂安治ですが、特に「賤ヶ岳の戦い」での活躍は目覚しく、その功名を讃えられ「賤ヶ岳の七本槍」の一人に数えられています。
「賤ヶ岳の戦い」の後、加藤嘉明や九鬼嘉隆らと共に水軍の指揮官を務め活躍。「関ヶ原の戦い」ではやむなく石田三成が率いる西軍に付きますが、戦いの最中に東軍に寝返ったため、脇坂家は処分を受けることはなく本領を安堵されました。
晩年は京都の西洞院で隠居。「臨松院」と号し、その生涯を終えました。
糟屋武則(かすやたけのり)
「賤ヶ岳の七本槍」七将の一人、「糟屋武則」は安土桃山時代から江戸時代にかけて活躍した武将・大名です。
糟屋武則は播磨国(現在の兵庫県南部)で、志村某の子として1562年(永禄5年)に生まれたとされています。 同じ「七本槍」の一員である、「加藤清正」や「福島正則」と比べると知名度が劣り、晩年は定かではありません。
糟屋という姓の他に、「粕屋」「加須屋」「賀須屋」などの姓も、武則の別名として伝わっています。その中でも、「加須屋真雄(かすやさねお)」という名乗りは有名です。
糟屋武則の母は戦国武将「小寺政職」の妹で、当初は糟屋朝貞へ嫁ぎ、朝正(友政)を産んだ後に離縁。その後、播磨国人の志村氏と再嫁し武則を産みますが、この時の夫と死別したため、武則を長男の朝正に託します。 異父弟の武則を義弟として教育してくれた朝正に恩を感じ、武則は志村姓を捨てて、「糟屋」と名乗るようになったとされています。
「三木合戦」で初陣を飾った糟屋武則は、「賤ヶ岳の戦い」で佐久間盛政配下の「宿屋七左衛門」を討ち取るなど大活躍。福島正則や加藤清正など、「賤ヶ岳の七本槍」と共に、「一番槍」の賞詞が渡されました。しかし、関ヶ原の戦いでは七本槍の中で唯一西軍に加わったため、戦後に改易されました。
糟屋武則の晩年は諸説あり正確なことはわかっていませんが、小禄という身分ながら、徳川家臣になったという説もあります。
片桐且元(かたぎりかつもと)
「賤ヶ岳の七本槍」七将の一人、「片桐且元」は安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将・大名です。
近江国浅井郡(現在の滋賀県長浜市)で、浅井長政に仕えた父「片桐直貞」の子として、1556年(弘治2年)に生まれ、1615年(元和元年)に死去。豊臣家の直参家臣として、若かりし頃より荒小姓として豊臣秀吉に仕えた人物です。秀吉からは「助佐」や「助作」と呼ばれ、弟に同国小泉藩主となった「片桐貞隆」がいます。
片桐且元は「賤ヶ岳の戦い」で目覚ましい武功をあげ、「七本槍」の一人として数えられるようになります。
豊臣秀吉の没後は、「豊臣秀頼」の後見だったことでも有名です。
関ヶ原の戦いでは秀頼を守るため、弱体化した豊臣家と徳川家の仲介を上手く果たすことで、終始に渡って豊臣家のために尽力したことで知られます。
しかし、「方広寺鐘銘事件」で徳川の内通者と疑われ、豊臣秀吉の側室であった淀君らと不和となり大坂城を退出。弟の貞隆らと共に居城の茨木に帰ってしまいます。大坂冬の陣では徳川方として参戦。翌年に起きた大坂夏の陣では、大坂城落城の際に、淀君や豊臣秀頼の助命を徳川家康に懇願するも叶わず、豊臣家は滅亡しました。
豊臣家の重臣として多大な功績を残した片桐且元ですが、大坂夏の陣の後、まもなく京都で病死。
肺を患っていたことによる病死とされていますが、一説では豊臣家が滅亡したことによる殉死との説もあります。
\ WEBでのご相談・ご依頼 受付中 /
簡単WEB査定【刀剣を売る】なら日晃堂にお任せください
今回の日晃堂コラムは、「賤ヶ岳の七本槍(しずがたけのしちほんやり)」についてご紹介させていただきました。
賤ヶ岳の七本槍とは、日本の歴史を変える大きな転機となった「賤ヶ岳の戦い」で活躍した、加藤清正、福島正則、加藤嘉明、平野長泰、脇坂安治、糟屋武則、片桐且元、七人の武将のことです。
豊臣秀吉はこの戦で勝利したのを機に、天下人として大きく前進しました。
「賤ヶ岳の戦い」は日本の歴史を語る上で欠かせない非常に重要な戦で、この七人の武将たちは、秀吉の子飼いの若武者達だったことでも有名ですね。
七本槍のような戦国武将たちの武器として使われてきた刀剣ですが、現代においても骨董品として高い価値があります。日晃堂では刀剣買取に力を入れており、相続品や手入れをしなくなった太刀、薙刀、脇差など、あらゆる刀剣がお買取の対象です。
「刀剣を売りたい」ということであれば、刀剣買取の日晃堂までぜひご連絡ください。
弊社の経験豊富な査定士が、価値に見合った買取価格をご提示させていただきます。
刀剣の買取に関する費用はすべて無料です。刀剣売るのが初めての方も、安心して日晃堂にお任せください!
お客様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
▼刀剣買取の関連記事は他にもございます。
下記の記事に興味を持った方は、合わせてご覧ください。
→【天下五剣】とは?日本刀の名刀5振についてご紹介します!
→【天下三名槍】とは?天下の名槍3振についてご紹介します!
無料のご相談・ご依頼はこちら
\ 日晃堂へのお問合せはお電話がおすすめです /
0120-961-491
刀剣買取なら、日晃堂にお任せください。
日本刀は100万円超える価値も多く、芸術品としても価値は高くなります。刀剣であれば刀、太刀、槍、薙刀、軍刀太刀、拵えなど品物を問わず、お持ちの刀剣を目利き致します。日晃堂の刀剣買取は全国対応、出張査定も無料ですので、ぜひご利用下さい。
関連記事
-

-
日本刀は売れる?買取相場や登録なし等、売れないケースなどを紹介
「売れない日本刀ってある?」「売れない日本刀はどうしたらいい?」 など、売れない日本刀について知りたい方のために情報をま…
-

-
刀剣の鑑定と査定の違い
刀剣の鑑定と刀剣査定は違う お客様から刀剣買取のご依頼をいただき刀剣の査定を行わせていただいている際に会話の流れで「査定…
-

-
【刀剣査定】刀剣の査定価格はどう決まる?
刀剣の査定は何を確認している? 近年では日本人のみならず海外にも数多くのファンを持つ日本刀。海外ではJAPANESE S…
カテゴリーから記事を探す
刀剣買取に
ついてのご相談・ご依頼はコチラ
丁寧に対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にお電話ください。
骨董品・古美術品の相談をする
0120-961-491
LINEやWEBでの依頼・相談も受付中