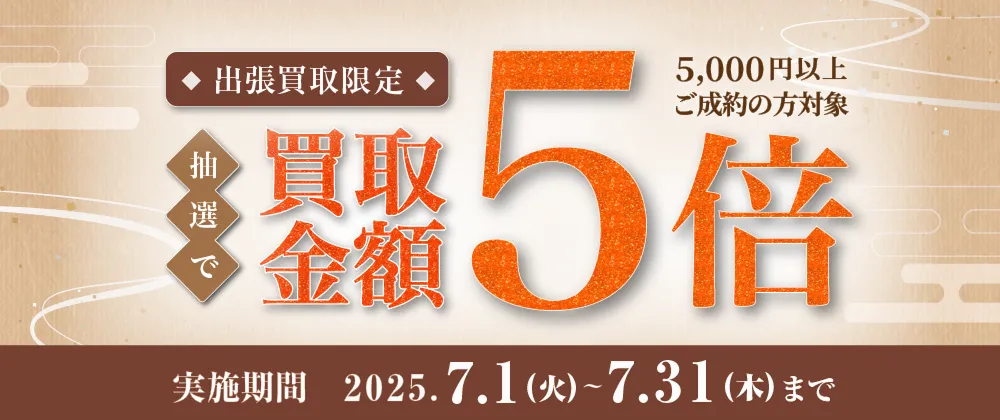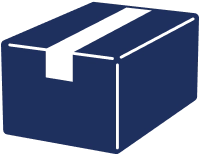寺内萬治郎(てらうちまんじろう)1890年–1964年

寺内萬治郎は、明治後期から昭和前期にかけて活動した日本の洋画家です。
当時、埼玉県の旧浦和市(のちのさいたま市浦和区など)は多くの画家がアトリエを構えた地だったことから、文学者の多い鎌倉市と並んで「鎌倉文士に浦和画家」と称されるほどでした。寺内もそんな“浦和画家”の1人です。
裸婦画を最も得意としており、日本の風土と時代性を意識したリアルなフォルムの裸婦画を追求し続けました。
また、“デッサンの神様”と称されるほど描画力に優れており、見事な描線で重厚かつ高貴な雰囲気を漂わせる作品を多く手がけました。
その一方で、後期は後進の育成にも熱心に取り組んでおり、その功績が讃えられて没後に勲四等旭日小綬章を授与されています。
中央画壇の発展に大きく貢献した“浦和画家”
寺内萬治郎は1890年、大阪府大阪市難波に生まれました。
15歳から大阪の洋画塾・天彩画塾で絵画を学び始め、20歳で上京。白馬会洋画研究所で近代洋画の巨匠・黒田清輝に師事しつつ、東京美術学校(現・東京藝術大学)西洋画科でも学びを深めました。
こうして絵の腕を磨いていった寺内は、1925年の帝展で「裸婦」が特選を受賞。翌年には無鑑査待遇を受けるまでに至りました。
さらには、これらの活躍が認められ、帝展審査員や光風会会員に推挙されるなど、華々しい画壇デビューを飾ります。
その後も順調に地位と名声を確立させていった寺内は、45歳の頃から浦和市針ヶ谷(現・さいたま市)に拠点を移し、よりいっそうの活躍を見せました。 旧帝展無鑑査有志によって結成された「第二部会」に参加し、また日本大学芸術学部および東京美術学校の講師に就任するなど、後進の指導にも力を入れるようになります。 もちろん、この間も並行して創作活動に励んでおり、1951年には「横臥裸婦」で日本芸術院賞を受賞。“裸婦の寺内”として洋画界に名を広めました。 これらの功績から、埼玉県美術科協会が結成された際に初代会長に任命され、さらには日本芸術院会員、日展理事なども歴任。長年にわたり、中央画壇を牽引しました。
寺内萬治郎の代表作
-
「横臥裸婦」
1951年に日本芸術院賞を受賞した、寺内萬治郎の代表作。
寺内はもとより裸婦画を得意としていたもの、1948年頃からさらにデッサンを重ね、裸婦画の技術を極めました。本作品はその集大成ともいえる大作であり、“裸婦の寺内”だからこその見事な描線で描かれています。 また、本作品に限らず、寺内の裸婦画は“日本の裸婦”を追求しているため、西洋画のものとは異なる小麦色の肌で描かれているのが特徴です。 -
「緑衣の婦人像」
机に肘をつき、神妙な面持ちで物思いにふける女性の姿が描かれた作品です。 寺内の代名詞といえる裸婦画ではないもの、女性の心の内を丸裸にしてしまうほど艶めいた画風で描かれているため、“服を纏った裸婦画”と捉えることもできそうな作品に仕上がっています。
そのほか、「赤いコート」「鏡」などが代表作として知られます。
高い専門性を誇る日晃堂の買取品目
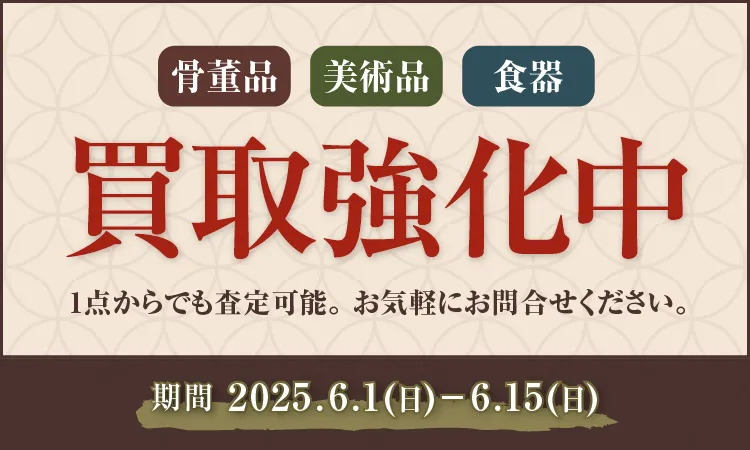
買取についてのご相談・ご依頼はコチラ
丁寧に対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にお電話ください。
骨董品・古美術品の相談をする
0120-961-491
はじめての方でも安心して
ご利用いただけます
日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです
-
01
お問い合わせ
電話、LINE、メールで
らくらく
お申し込み。 -
02
査定
出張買取は全国どこでも。
店頭や宅配もお気軽に。 -
03
お支払い
即!その場で現金お手渡し。
※宅配買取は振込
ご都合に合わせて選べる
買取方法
他店で断られた状態不良の
お品物でも
お気軽にお問合せください
独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。
ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ
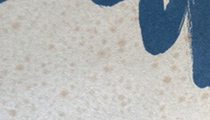
シミ

虫食い
骨董品・食器買取における対応エリア
日本全国どこからでもご利用いただけます。