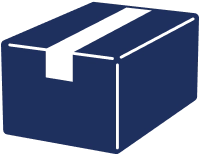松岡映丘(まつおかえいきゅう)1881年–1938年

松岡映丘は、明治の末から昭和にかけて活躍した日本画家です。
日本画が変革の時を迎えようとしていた時代、あくまでも古典に立脚した世界観を創造することに精魂を傾け、平安・鎌倉期に描かれた絵巻物を深く研究し、さらには平安時代に確立された有識故実を学んで見識を深め、そのうえで古典的な絵画にモダニズムのエッセンスを加えた作品を生み出しました。
その作品は「新興やまと絵」と呼ばれており、高い価値を誇ります。
古典をもとに「新興やまと絵」を創出した日本画家
1881年、松岡映丘は兵庫県に生まれました。
医学や儒学、文学、はたまた民俗学といったさまざまな学問の分野で活躍する芸術家・学者を家族に持ち(兄のひとりは民俗学者の柳田國男)、その縁もあって幼少の頃から芸術や古典に触れて育ちます。
1899年、東京美術学校の日本画科に入学しますが、その前から絵は狩野派の流れをくむ橋本雅邦に手ほどきを受け、さらに絵巻物や有識故実の研究を進め、「新興やまと絵」の基礎を築いていました。 美術学校に入学後は教授の寺崎広業らに学びつつ、のちに新聞小説の挿絵画家として一世を風靡することになる梶田半古らとともに「歴史風俗画会」で活動します。 1904年、首席で卒業を果たした映丘は美術講師の職を選び、東京美術学校で教授を務めます。
そんな映丘が本格的に画家として活動を開始したのは1912年のこと。 『源氏物語』から題材をとった「宇治の宮の姫君たち」が文展で入選を果たします。 その後も、文展を中心にさまざまな作品を発表。 単なる古典主義ではなく、現代的な眼差しで事物を見つめた作品は高く評価されました。 1921年には、映丘の理論を実践するための新興大和絵会を結成。 10年後には解散してしまいますが、映丘はその10年間を有効に使いきりました。 研究に没頭し、絵巻物の解説書を著し、学識をさらに深めて絵画の研鑚を積みます。 その後、1930年代には帝国美術院、帝国芸術院の会員になるなど画壇の重鎮のひとりとして活躍しますが、1938年に死去。56歳で生涯を閉じました。
松岡映丘の代表作
-
「右大臣実朝」
1932年の作品で、鎌倉幕府第3代将軍・源実朝を描いています。
秀麗な顔立ちの実朝が正装して牛車に乗り、憂愁を帯びた目でどこかを見つめています。 御家人たちの権力闘争によって殺伐としていた鎌倉時代、実朝は争いごとを好まず、和歌を愛する芸術家タイプの人物でした。しかし将軍であるがゆえに、彼もまた否応なく骨肉の争いに巻き込まれます。1219年1月27日、実朝は鶴岡八幡宮を拝賀のために訪れました。敵対勢力にそそのかされた甥の公暁が、彼を暗殺するために待ち受けているとも知らず……。 映丘は、知らぬ間に最期の日を迎えてしまった実朝の姿を、絵巻物の時代から続く伝統的な画風で描きました。しかしその表情には、どこか悲劇を予期しているかのような複雑な表情が浮かんでおり、現代的な風味が加えられています。 -
「千草の丘」
1926年の作品です。涼やかな秋の情景の中に、鮮やかな色合いの着物をまとった女性がほぼ等身大のサイズで描かれています。 女性のモデルになったのは、絶世の美女として絶大な人気を誇った新劇の女優、水谷八重子(初代)。空がゆっくりと暮れなずんでいく中、天地がきらめいて風景がくっきりと浮かび上がり、微笑する女性のたおやかな美しさを引き立たせます。
その他、「伊香保の沼」「神宮親謁」などが代表作として知られています。
高い専門性を誇る日晃堂の買取品目
松岡映丘 作品
買取についてのご相談・ご依頼はコチラ
丁寧に対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にお電話ください。
骨董品・古美術品の相談をする
0120-961-491
LINEやWEBでの依頼・相談も受付中
はじめての方でも安心して
ご利用いただけます
日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです
-
01
お問い合わせ
電話、LINE、メールで
らくらく
お申し込み。 -
02
査定
出張買取は全国どこでも。
店頭や宅配もお気軽に。 -
03
お支払い
即!その場で現金お手渡し。
※宅配買取は振込
ご都合に合わせて選べる
買取方法
システムメンテナンスのため、2025年12月12日(金)より新規の宅配買取受付を一時停止させていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
他店で断られた状態不良の
お品物でも
お気軽にお問合せください
独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。
ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ
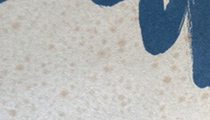
シミ

虫食い
骨董品・美術品買取
対応エリア
日晃堂では全国どこでも無料で買取いたします。
-

北海道

青森県

秋田県
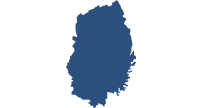
岩手県
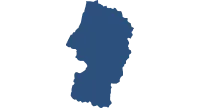
山形県
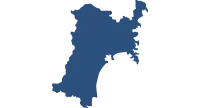
宮城県

福島県
-

東京都

神奈川県

千葉県

埼玉県

茨城県
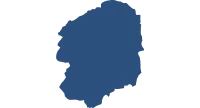
栃木県
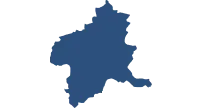
群馬県

山梨県
-
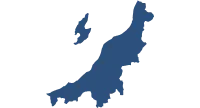
新潟県
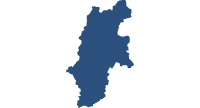
長野県

富山県

石川県

福井県
-

愛知県

静岡県
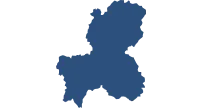
岐阜県

三重県
-
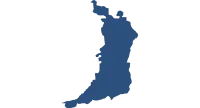
大阪府
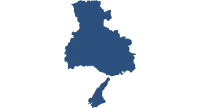
兵庫県
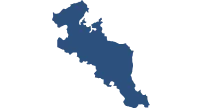
京都府

滋賀県
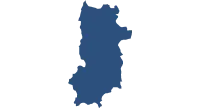
奈良県
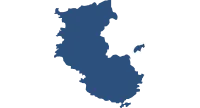
和歌山県
-

鳥取県

島根県
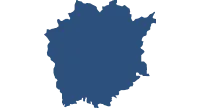
岡山県

広島県

山口県
-

香川県

徳島県

高知県

愛媛県
-

福岡県

佐賀県

長崎県
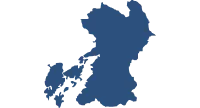
熊本県

大分県
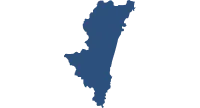
宮崎県
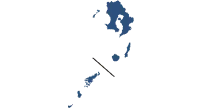
鹿児島県

沖縄県
北海道の対応エリア
- 市
- 札幌市内全域(中央区、東区、北区、白石区、厚別区、手稲区、南区、西区、豊平区、清田区)、函館市、旭川市、室蘭市、小樽市、帯広市、北見市、釧路市、岩見沢市、網走市、石狩市、留萌市、北斗市、夕張市、稚内市、美唄市、芦別市、苫小牧市、赤平市、北広島市、士別市、紋別市、伊達市、江別市、名寄市、根室市、千歳市、登別市、三笠市、砂川市、滝川市、深川市、歌志内市、富良野市、恵庭市
- 町村
- 道南・道央(浦河郡浦河町、白老郡白老町、山越郡長万部町、磯谷郡蘭越町、虻田郡真狩村、虻田郡喜茂別町、虻田郡留寿都村、虻田郡ニセコ町、虻田郡倶知安町、虻田郡京極町、虻田郡洞爺湖町、虻田郡豊浦町、雨竜郡秩父別町、雨竜郡北竜町、雨竜郡妹背牛町、雨竜郡沼田町、雨竜郡雨竜町、雨竜郡幌加内町、茅部郡鹿部町、茅部郡森町、奥尻郡奥尻町、久遠郡せたな町、亀田郡七飯町、古宇郡神恵内村、古宇郡泊村、古平郡古平町、沙流郡平取町、沙流郡日高町、寿都郡寿都町、寿都郡黒松内町、松前郡松前町、松前郡福島町、爾志郡乙部町、上磯郡木古内町、上磯郡知内町、新冠郡新冠町、石狩郡当別町、石狩郡新篠津村、瀬棚郡今金町、積丹郡積丹町、二海郡八雲町、島牧郡島牧村、幌泉郡えりも町、有珠郡壮瞥町、日高郡新ひだか町、夕張郡由仁町、夕張郡長沼町、夕張郡栗山町、余市郡赤井川村、余市郡仁木町、余市郡余市町、様似郡様似町、檜山郡上ノ国町、檜山郡江差町、檜山郡厚沢部町、岩内郡岩内町、岩内郡共和町、樺戸郡月形町、樺戸郡新十津川町、樺戸郡浦臼町) 道北・道東(阿寒郡鶴居村、広尾郡広尾町、広尾郡大樹町、河西郡中札内村、河西郡更別村、河西郡芽室町、河東郡士幌町、河東郡音更町、河東郡鹿追町、河東郡上士幌町、留萌郡小平町、目梨郡羅臼町、釧路郡釧路町、厚岸郡浜中町、厚岸郡厚岸町、斜里郡小清水町、斜里郡斜里町、斜里郡清里町、十勝郡浦幌町、宗谷郡猿払村、上川郡東神楽町、上川郡鷹栖町、上川郡美瑛町、上川郡新得町、上川郡比布町、上川郡当麻町、上川郡上川町、上川郡愛別町、上川郡東川町、上川郡剣淵町、上川郡和寒町、上川郡下川町、上川郡清水町、野付郡別海町、常呂郡置戸町、常呂郡訓子府町、常呂郡佐呂間町、川上郡弟子屈町、川上郡標茶町、増毛郡増毛町、中川郡音威子府村、中川郡中川町、中川郡美深町、中川郡池田町、中川郡豊頃町、中川郡幕別町、中川郡本別町、白糠郡白糠町、標津郡標津町、網走郡美幌町、標津郡中標津町、網走郡大空町、網走郡津別町、紋別郡湧別町、紋別郡遠軽町、紋別郡興部町、紋別郡西興部村、紋別郡雄武町、紋別郡滝上町、礼文郡礼文町、利尻郡利尻富士町、利尻郡利尻町、勇払郡むかわ町、勇払郡安平町、勇払郡占冠村、勇払郡厚真町、足寄郡足寄町、足寄郡陸別町、苫前郡苫前町、苫前郡羽幌町、苫前郡初山別村、天塩郡天塩町、天塩郡遠別町、天塩郡幌延町、天塩郡豊富町、枝幸郡中頓別町、枝幸郡浜頓別町、枝幸郡枝幸町、空知郡上富良野町、空知郡奈井江町、空知郡上砂川町、空知郡南幌町、空知郡南富良野町、空知郡中富良野町)
青森県の対応エリア
- 市
- 青森市、八戸市、黒石市、弘前市、十和田市、五所川原市、むつ市、三沢市、平川市、つがる市
- 町村
- 東津軽郡今別町、東津軽郡平内町、東津軽郡外ヶ浜町、東津軽郡蓬田村、西津軽郡深浦町、西津軽郡鰺ヶ沢町、中津軽郡西目屋村、南津軽郡大鰐町、南津軽郡藤崎町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡鶴田町、北津軽郡中泊町、北津軽郡板柳町、上北郡野辺地町、上北郡七戸町、上北郡横浜町、上北郡六戸町、上北郡六ヶ所村、上北郡東北町、上北郡おいらせ町、下北郡佐井村、下北郡東通村、下北郡風間浦村、下北郡大間町、三戸郡三戸町、三戸郡田子町、三戸郡五戸町、三戸郡階上町、三戸郡南部町、三戸郡新郷村
秋田県の対応エリア
- 市
- 秋田市、横手市、大館市、能代市、湯沢市、鹿角市、男鹿市、潟上市、大仙市、由利本荘市、にかほ市、仙北市、北秋田市
- 町村
- 北秋田郡上小阿仁村、鹿角郡小坂町、山本郡三種町、山本郡八峰町、山本郡藤里町、南秋田郡八郎潟町、南秋田郡井川町、南秋田郡五城目町、南秋田郡大潟村、雄勝郡東成瀬村、雄勝郡羽後町、仙北郡美郷町
岩手県の対応エリア
- 市
- 盛岡市、大船渡市、花巻市、宮古市、久慈市、遠野市、北上市、陸前高田市、一関市、二戸市、八幡平市、釜石市、奥州市, 滝沢市
- 町村
- 岩手郡岩手町、岩手郡雫石町、岩手郡葛巻町、紫波郡矢巾町、紫波郡紫波町、西磐井郡平泉町、気仙郡住田町、気仙郡三陸町、下閉伊郡普代村、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、上閉伊郡大槌町、九戸郡洋野町、九戸郡九戸村、九戸郡軽米町、九戸郡野田村、二戸郡一戸町、和賀郡西和賀町
山形県の対応エリア
- 市
- 山形市、天童市、鶴岡市、南陽市、米沢市、新庄市、寒河江市、酒田市、村山市、長井市、上山市、東根市、尾花沢市
- 町村
- 西村山郡西川町、西村山郡河北町、西村山郡大江町、西村山郡朝日町、北村山郡大石田町、東村山郡山辺町、東村山郡中山町、飽海郡遊佐町、最上郡最上町、最上郡真室川町、最上郡舟形町、最上郡金山町、最上郡大蔵村、最上郡戸沢村、最上郡鮭川村、東置賜郡川西町、東置賜郡高畠町、西置賜郡飯豊町、西置賜郡小国町、西置賜郡白鷹町、東田川郡庄内町、東田川郡三川町
宮城県の対応エリア
- 市
- 仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区)、塩竈市、石巻市、白石市、名取市、気仙沼市、多賀城市、岩沼市、角田市、登米市、東松島市、大崎市、栗原市、富谷市、塩竃市
- 町村
- 刈田郡七ヶ宿町、刈田郡蔵王町、柴田郡村田町、柴田郡柴田町、柴田郡大河原町、柴田郡川崎町、本吉郡南三陸町、亘理郡山元町、亘理郡亘理町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、宮城郡松島町、黒川郡大郷町、黒川郡大和町、黒川郡大衡村、加美郡加美町、加美郡色麻町、遠田郡美里町、遠田郡涌谷町、牡鹿郡女川町、伊具郡
福島県の対応エリア
- 市
- 会津若松市、福島市、いわき市、郡山市、須賀川市、白河市、相馬市、二本松市、喜多方市、南相馬市、伊達市、田村市、本宮市
- 町村
- 伊達郡桑折町、伊達郡川俣町、伊達郡国見町、安達郡大玉村、岩瀬郡天栄村、岩瀬郡鏡石町、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、南会津郡下郷町、耶麻郡西会津町、耶麻郡猪苗代町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡北塩原村、河沼郡柳津町、河沼郡湯川村、河沼郡会津坂下町、大沼郡昭和村、大沼郡三島町、大沼郡会津美里町、大沼郡金山町、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、東白川郡塙町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、東白川郡鮫川村、石川郡平田村、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村
東京都の対応エリア
- 東京都23区
- 港区、新宿区、大田区、渋谷区、杉並区、墨田区、品川区、台東区、世田谷区、豊島区、千代田区、練馬区、中野区、足立区、目黒区、板橋区、江戸川区、荒川区、葛飾区、北区、江東区、中央区、文京区
- 市
- 立川市、武蔵野市、八王子市、青梅市、三鷹市、昭島市、府中市、町田市、調布市、小平市、小金井市、東村山市、日野市、国立市、福生市、国分寺市、東大和市、狛江市、東久留米市、清瀬市、多摩市、武蔵村山市、羽村市、稲城市、西東京市、あきる野市
神奈川県の対応エリア
- 市
- 横浜市内全域(神奈川区、鶴見区、中区、南区、西区、磯子区、金沢区、保土ケ谷区、戸塚区、港南区、旭区、港北区、瀬谷区、栄区、緑区、青葉区、泉区、都筑区)、川崎市内全域(川崎区、中原区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市内全域(緑区、南区、中央区)、平塚市、鎌倉市、横須賀市、小田原市、藤沢市、逗子市、相模原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、三浦市、伊勢原市、海老名市、大和市、南足柄市、綾瀬市、座間市
- 町村
- 三浦郡葉山町、中郡大磯町、中郡二宮町、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡中井町、足柄上郡開成町、足柄下郡箱根町、足柄上郡山北町、足柄下郡湯河原町、足柄下郡真鶴町、愛甲郡清川村、愛甲郡愛川町
千葉県の対応エリア
- 市
- 千葉市内全域(中央区、稲毛区、花見川区、緑区、若葉区、美浜区)、市川市、船橋市、銚子市、木更津市、松戸市、館山市、茂原市、野田市、佐倉市、東金市、成田市、習志野市、柏市、旭市、市原市、勝浦市、八千代市、我孫子市、流山市、鎌ケ谷市、鴨川市、富津市、浦安市、君津市、袖ケ浦市、四街道市、印西市、白井市、八街市、南房総市、富里市、香取市、匝瑳市、いすみ市、山武市、大網白里市
- 町村
- 印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、安房郡鋸南町、香取郡多古町、香取郡神崎町、香取郡東庄町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、山武郡九十九里町、長生郡睦沢町、長生郡一宮町、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、長生郡長生村、夷隅郡御宿町、夷隅郡大多喜町
埼玉県の対応エリア
- 市
- さいたま市内全域(西区、大宮区、北区、中央区、桜区、見沼区、南区、浦和区、岩槻区、緑区)、熊谷市、川口市、川越市、秩父市、所沢市、行田市、加須市、飯能市、東松山市、春日部市、本庄市、羽生市、狭山市、鴻巣市、上尾市、草加市、深谷市、蕨市、越谷市、入間市、戸田市、志木市、朝霞市、新座市、桶川市、和光市、北本市、久喜市、富士見市、三郷市、八潮市、坂戸市、幸手市、蓮田市、日高市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、白岡市、吉川市
- 町村
- 入間郡三芳町、入間郡越生町、入間郡毛呂山町、北足立郡伊奈町、大里郡寄居町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡滑川町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、比企郡川島町、比企郡ときがわ町、秩父郡皆野町、秩父郡横瀬町、秩父郡長瀞町、秩父郡東秩父村、秩父郡小鹿野町、児玉郡上里町、児玉郡神川町、児玉郡美里町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町、北葛飾郡松伏町
茨城県の対応エリア
- 市
- 水戸市、土浦市、日立市、古河市、結城市、石岡市、下妻市、龍ケ崎市、常総市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、高萩市、牛久市、つくば市、取手市、鹿嶋市、潮来市、ひたちなか市、常陸大宮市、守谷市、筑西市、坂東市、那珂市、かすみがうら市、稲敷市、神栖市、行方市、桜川市、つくばみらい市、鉾田市、小美玉市
- 町村
- 東茨城郡大洗町、東茨城郡茨城町、東茨城郡城里町、久慈郡大子町、那珂郡東海村、稲敷郡阿見町、稲敷郡美浦村、稲敷郡河内町、猿島郡境町、猿島郡五霞町、結城郡八千代町、北相馬郡利根町
栃木県の対応エリア
- 市
- 宇都宮市、栃木市、足利市、鹿沼市、日光市、佐野市、真岡市、大田原市、小山市、那須塩原市、矢板市、さくら市、下野市、那須烏山市
- 町村
- 河内郡上三川町、芳賀郡茂木町、芳賀郡益子町、芳賀郡芳賀町、芳賀郡市貝町、下都賀郡野木町、下都賀郡壬生町、塩谷郡高根沢町、塩谷郡塩谷町、那須郡那珂川町、那須郡那須町
群馬県の対応エリア
- 市
- 前橋市、桐生市、高崎市、太田市、沼田市、伊勢崎市、渋川市、藤岡市、みどり市、館林市、安中市、富岡市
- 町村
- 北群馬郡吉岡町、北群馬郡榛東村、多野郡神流町、多野郡上野村、甘楽郡南牧村、甘楽郡甘楽町、甘楽郡下仁田町、吾妻郡長野原町、吾妻郡中之条町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡高山村、吾妻郡草津町、吾妻郡東吾妻町、利根郡川場村、利根郡片品村、利根郡みなかみ町、利根郡昭和村、佐波郡玉村町、邑楽郡明和町、邑楽郡邑楽町、邑楽郡千代田町、邑楽郡板倉町、邑楽郡大泉町
山梨県の対応エリア
- 市
- 南アルプス市、都留市、韮崎市、山梨市、富士吉田市、大月市、北杜市、甲斐市、甲府市、上野原市、中央市、甲州市、笛吹市
- 町村
- 中巨摩郡昭和町、南巨摩郡身延町、南巨摩郡南部町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡富士川町、西八代郡市川三郷町、南都留郡西桂町、南都留郡道志村、南都留郡山中湖村、南都留郡忍野村、南都留郡富士河口湖町、南都留郡鳴沢村、北都留郡丹波山村、北都留郡小菅村
新潟県の対応エリア
- 市
- 新潟市全域(北区、中央区、東区、江南区、西蒲区、南区、西区、秋葉区)、三条市、柏崎市、長岡市、小千谷市、新発田市、十日町市、見附市、加茂市、燕市、村上市、妙高市、五泉市、上越市、糸魚川市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、阿賀野市
- 町村
- 西蒲原郡弥彦村、南蒲原郡田上町、北蒲原郡聖籠町、東蒲原郡阿賀町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村、岩船郡粟島浦村、岩船郡関川村
長野県の対応エリア
- 市
- 長野市、上田市、松本市、飯田市、諏訪市、岡谷市、安曇野市、小諸市、伊那市、須坂市、中野市、駒ヶ根市、飯山市、大町市、塩尻市、佐久市、茅野市、千曲市、東御市、駒ケ根市
- 町村
- 南佐久郡小海町、南佐久郡川上村、南佐久郡南相木村、南佐久郡南牧村、南佐久郡北相木村、南佐久郡佐久穂町、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、北佐久郡立科町、小県郡青木村、小県郡長和町、諏訪郡富士見町、諏訪郡原村、諏訪郡下諏訪町、上伊那郡箕輪町、上伊那郡飯島町、上伊那郡辰野町、上伊那郡中川村、上伊那郡南箕輪村、上伊那郡宮田村、下伊那郡高森町、下伊那郡松川町、下伊那郡阿智村、下伊那郡平谷村、下伊那郡売木村、下伊那郡阿南町、下伊那郡根羽村、下伊那郡天龍村、下伊那郡大鹿村、下伊那郡下條村、下伊那郡泰阜村、下伊那郡豊丘村、下伊那郡喬木村、木曽郡木祖村、木曽郡南木曽町、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町、木曽郡上松町、木曽郡王滝村、東筑摩郡生坂村、東筑摩郡麻績村、東筑摩郡朝日村、東筑摩郡筑北村、東筑摩郡山形村、北安曇郡松川村、北安曇郡池田町、北安曇郡小谷村、北安曇郡白馬村、埴科郡坂城町、上高井郡高山村、上高井郡小布施町、下高井郡山ノ内町、下高井郡野沢温泉村、下高井郡木島平村、下水内郡栄村、上水内郡小川村、上水内郡信濃町、上水内郡飯綱町
富山県の対応エリア
- 市
- 富山市、小矢部市、氷見市、魚津市、射水市、高岡市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市
- 町村
- 下新川郡朝日町、下新川郡入善町、中新川郡上市町、中新川郡舟橋村、中新川郡立山町
石川県の対応エリア
- 市
- 金沢市、小松市、七尾市、珠洲市、加賀市、輪島市、かほく市、羽咋市、白山市、野々市市、能美市
- 町村
- 能美郡川北町、鹿島郡中能登町、河北郡内灘町、河北郡津幡町、羽咋郡宝達志水町、羽咋郡志賀町、鳳珠郡能登町、鳳珠郡穴水町
福井県の対応エリア
- 市
- 福井市、あわら市、小浜市、敦賀市、勝山市、大野市、坂井市、鯖江市、越前市
- 町村
- 吉田郡永平寺町、三方上中郡若狭町、南条郡南越前町、今立郡池田町、三方郡美浜町、大飯郡高浜町、大飯郡おおい町、丹生郡越前町
愛知県の対応エリア
- 市
- 名古屋市全域(中区、南区、東区、北区、西区、中村区、千種区、瑞穂区、昭和区、熱田区、天白区、港区、中川区、緑区、名東区、守山区)、岡崎市、豊橋市、瀬戸市、半田市、一宮市、豊川市、津島市、春日井市、碧南市、西尾市、長久手市、豊田市、みよし市、安城市、清須市、稲沢市、刈谷市、犬山市、蒲郡市、日進市、江南市、小牧市、常滑市、東海市、大府市、豊明市、新城市、知立市、知多市、高浜市、岩倉市、尾張旭市、田原市、愛西市、北名古屋市、弥富市、あま市
- 町村
- 愛知郡東郷町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、西春日井郡豊山町、海部郡大治町、海部郡飛島村、海部郡蟹江町、知多郡東浦町、知多郡武豊町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡阿久比町、北設楽郡設楽町、北設楽郡豊根村、北設楽郡東栄町、額田郡幸田町
静岡県の対応エリア
- 市
- 静岡市内全域(駿河区、葵区、清水区)、浜松市内全域(中央区、、浜名区天竜区)、熱海市、沼津市、富士宮市、伊東市、三島市、富士市、島田市、焼津市、掛川市、磐田市、御殿場市、藤枝市、袋井市、裾野市、湖西市、下田市、御前崎市、牧之原市、伊豆市、伊豆の国市、菊川市
- 町村
- 賀茂郡河津町、賀茂郡東伊豆町、賀茂郡松崎町、賀茂郡南伊豆町、賀茂郡西伊豆町、駿東郡清水町、駿東郡小山町、駿東郡長泉町、田方郡函南町、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町、周智郡森町
岐阜県の対応エリア
- 市
- 岐阜市、高山市、多治見市、大垣市、中津川市、関市、瑞浪市、羽島市、美濃市、美濃加茂市、土岐市、恵那市、可児市、各務原市、瑞穂市、飛騨市、山県市、郡上市、本巣市、海津市、下呂市
- 町村
- 羽島郡笠松町、羽島郡岐南町、養老郡養老町、不破郡関ケ原町、不破郡垂井町、安八郡輪之内町、安八郡神戸町、安八郡安八町、揖斐郡大野町、揖斐郡池田町、揖斐郡揖斐川町、本巣郡北方町、加茂郡富加町、加茂郡川辺町、加茂郡八百津町、加茂郡白川町、加茂郡七宗町、加茂郡坂祝町、加茂郡東白川村、大野郡白川村、可児郡御嵩町
三重県の対応エリア
- 市
- 津市、四日市市、志摩市、伊勢市、鈴鹿市、伊賀市、名張市、亀山市、尾鷲市、桑名市、鳥羽市、いなべ市、熊野市、松阪市
- 町村
- 南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡朝日町、三重郡菰野町、三重郡川越町、多気郡明和町、多気郡大台町、多気郡多気町、度会郡大紀町、度会郡玉城町、度会郡度会町、度会郡南伊勢町、北牟婁郡紀北町
大阪府の対応エリア
- 市
- 大阪市(都島区、福島区、天王寺区、西区、港区、大正区、此花区、浪速区、西淀川区、中央区、東成区、生野区、東淀川区、城東区、旭区、住吉区、東住吉区、西成区、阿倍野区、鶴見区、淀川区、平野区、北区、住之江区)、東大阪市、岸和田市、豊中市、堺市(堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区)、藤井寺市、高槻市、泉南市、吹田市、泉大津市、池田市、守口市、枚方市、河内長野市、貝塚市、八尾市、茨木市、箕面市、富田林市、羽曳野市、寝屋川市、泉佐野市、大東市、和泉市、松原市、柏原市、摂津市、四條畷市、高石市、交野市、門真市、大阪狭山市
- 町村
- 泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、泉北郡忠岡町、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、三島郡島本町、南河内郡河南町、南河内郡太子町、南河内郡千早赤阪村
兵庫県の対応エリア
- 市
- 神戸市内全域(灘区、長田区、兵庫区、東灘区、北区、垂水区、須磨区、西区、中央区)、尼崎市、明石市、姫路市、加東市、洲本市、芦屋市、西宮市、相生市、伊丹市、加古川市、赤穂市、豊岡市、宝塚市、西脇市、高砂市、川西市、三木市、小野市、加西市、丹波篠山市、三田市、たつの市、丹波市、養父市、朝来市、淡路市、宍粟市、南あわじ市
- 町村
- 加古郡播磨町、加古郡稲美町、多可郡多可町、神崎郡福崎町、神崎郡市川町、神崎郡神河町、揖保郡太子町、川辺郡猪名川町、赤穂郡上郡町、美方郡新温泉町、美方郡香美町、佐用郡佐用町
京都府の対応エリア
- 市
- 京都市内全域(伏見区、山科区、東山区、西京区、東山区、北区、上京区、南区、中京区、下京区、右京区、左京区)、亀岡市、舞鶴市、長岡京市、城陽市、綾部市、宇治市、宮津市、京丹後市、福知山市、南丹市、向日市、八幡市、京田辺市、木津川市
- 町村
- 久世郡久御山町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、乙訓郡大山崎町、相楽郡笠置町、相楽郡精華町、相楽郡南山城村、相楽郡和束町、綴喜郡宇治田原町、船井郡京丹波町、与謝郡与謝野町、与謝郡伊根町
滋賀県の対応エリア
- 市
- 草津市、近江八幡市、大津市、長浜市、彦根市、栗東市、守山市、甲賀市、湖南市、米原市、高島市、野洲市、東近江市
- 町村
- 蒲生郡竜王町、蒲生郡日野町、愛知郡愛荘町、蒲生郡竜王町、犬上郡多賀町、犬上郡甲良町、犬上郡豊郷町
奈良県の対応エリア
- 市
- 奈良市、大和郡山市、大和高田市、葛城市、五條市、橿原市、桜井市、宇陀市、天理市、生駒市、香芝市、御所市
- 町村
- 高市郡明日香村、高市郡高取町、生駒郡三郷町、生駒郡平群町、生駒郡安堵町、生駒郡斑鳩町、磯城郡三宅町、磯城郡田原本町、磯城郡川西町、宇陀郡御杖村、宇陀郡曽爾村、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛城郡河合町、北葛城郡上牧町、山辺郡山添村、吉野郡十津川村、吉野郡大淀町、吉野郡吉野町、吉野郡東吉野村、吉野郡黒滝村、吉野郡上北山村、吉野郡天川村、吉野郡下市町、吉野郡野迫川村、吉野郡下北山村、吉野郡川上村
和歌山県の対応エリア
- 市
- 和歌山市、御坊市、田辺市、橋本市、紀の川市、有田市、新宮市、海南市、岩出市
- 町村
- 東牟婁郡那智勝浦町、東牟婁郡太地町、東牟婁郡古座川町、東牟婁郡北山村、東牟婁郡串本町、有田郡湯浅町、有田郡広川町、有田郡有田川町、日高郡美浜町、日高郡日高町、日高郡由良町、日高郡印南町、日高郡みなべ町、日高郡日高川町、西牟婁郡白浜町、西牟婁郡上富田町、西牟婁郡すさみ町、海草郡紀美野町
鳥取県の対応エリア
- 市
- 鳥取市、境港市、倉吉市、米子市
- 町村
- 八頭郡八頭町、八頭郡若桜町、八頭郡智頭町、岩美郡岩美町、東伯郡北栄町、東伯郡湯梨浜町、東伯郡三朝町、東伯郡琴浦町、西伯郡南部町、西伯郡大山町、西伯郡日吉津村、西伯郡伯耆町、日野郡江府町、日野郡日野町、日野郡日南町
島根県の対応エリア
- 市
- 松江市、浜田市、雲南市、益田市、出雲市、安来市、江津市、大田市
- 町村
- 仁多郡奥出雲町、隠岐郡知夫村、隠岐郡海士町、隠岐郡隠岐の島町、隠岐郡西ノ島町、邑智郡邑南町、邑智郡川本町、邑智郡美郷町、飯石郡飯南町、鹿足郡吉賀町、鹿足郡津和野町
岡山県の対応エリア
- 市
- 岡山市内全域(中区、南区、北区、東区)、笠岡市、瀬戸内市、津山市、玉野市、倉敷市、備前市、井原市、浅口市、高梁市、新見市、総社市、赤磐市、美作市、真庭市
- 町村
- 都窪郡早島町、和気郡和気町、浅口郡里庄町、真庭郡新庄村、加賀郡吉備中央町、小田郡矢掛町、勝田郡奈義町、勝田郡勝央町、苫田郡鏡野町、久米郡久米南町、久米郡美咲町、英田郡西粟倉村
広島県の対応エリア
- 市
- 広島市内全域(中区、西区、南区、東区、佐伯区、安佐北区、安芸区、安佐南区)、竹原市、廿日市市、三原市、江田島市、呉市、大竹市、福山市、府中市、三次市、尾道市、庄原市、東広島市、安芸高田市
- 町村
- 山県郡北広島町、山県郡安芸太田町、安芸郡坂町、安芸郡海田町、安芸郡府中町、安芸郡熊野町、神石郡神石高原町、世羅郡世羅町、豊田郡大崎上島町
山口県の対応エリア
- 市
- 下関市、周南市、山口市、防府市、長門市、岩国市、光市、山陽小野田市、下松市、柳井市、美祢市、萩市、宇部市
- 町村
- 玖珂郡和木町、大島郡周防大島町、阿武郡阿武町、熊毛郡上関町、熊毛郡平生町、熊毛郡田布施町
香川県の対応エリア
- 市
- 丸亀市、高松市、さぬき市、三豊市、善通寺市、観音寺市、坂出市、東かがわ市
- 町村
- 小豆郡小豆島町、小豆郡土庄町、香川郡直島町、綾歌郡綾川町、綾歌郡宇多津町、木田郡三木町、仲多度郡多度津町、仲多度郡琴平町、仲多度郡まんのう町
徳島県の対応エリア
- 市
- 徳島市、小松島市、三好市、鳴門市、吉野川市、阿波市、阿南市、美馬市
- 町村
- 名西郡神山町、名東郡佐那河内村、名西郡石井町、那賀郡那賀町、勝浦郡上勝町、勝浦郡勝浦町、海部郡海陽町、海部郡美波町、海部郡牟岐町、板野郡北島町、板野郡松茂町、板野郡板野町、板野郡藍住町、板野郡上板町、三好郡東みよし町、美馬郡つるぎ町
高知県の対応エリア
- 市
- 室戸市、宿毛市、安芸市、高知市、香美市、土佐市、須崎市、南国市、土佐清水市、四万十市、香南市
- 町村
- 土佐郡土佐町、土佐郡大川村、安芸郡芸西村、安芸郡奈半利町、安芸郡馬路村、安芸郡東洋町、安芸郡安田町、安芸郡田野町、安芸郡北川村、幡多郡三原村、幡多郡大月町、幡多郡黒潮町、長岡郡大豊町、長岡郡本山町、吾川郡仁淀川町、吾川郡いの町、高岡郡中土佐町、高岡郡越知町、高岡郡佐川町、高岡郡日高村、高岡郡四万十町、高岡郡檮原町、高岡郡津野町
愛媛県の対応エリア
- 市
- 松山市、伊予市、宇和島市、今治市、大洲市、東温市、新居浜市、西条市、八幡浜市、四国中央市、西予市
- 町村
- 越智郡上島町、上浮穴郡久万高原町、伊予郡砥部町、伊予郡松前町、喜多郡内子町、南宇和郡愛南町、北宇和郡松野町、北宇和郡鬼北町、西宇和郡伊方町
福岡県の対応エリア
- 市
- 福岡市内全域(東区、南区、早良区、中央区、博多区、西区、城南区)、北九州市内全域(若松区、戸畑区、門司区、八幡東区、八幡西区、小倉南区、小倉北区)、筑後市、太宰府市、福津市、久留米市、直方市、大牟田市、田川市、柳川市、小郡市、糸島市、飯塚市、八女市、大川市、豊前市、中間市、行橋市、朝倉市、筑紫野市、大野城市、宗像市、春日市、うきは市、古賀市、宮若市、嘉麻市、みやま市、那珂川市
- 町村
- 田川郡添田町、田川郡香春町、田川郡赤村、田川郡川崎町、田川郡糸田町、田川郡大任町、田川郡福智町、八女郡広川町、糟屋郡久山町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡須惠町、糟屋郡宇美町、糟屋郡新宮町、糟屋郡志免町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡遠賀町、鞍手郡鞍手町、鞍手郡小竹町、三潴郡大木町、三井郡大刀洗町、嘉穂郡桂川町、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村、京都郡苅田町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、築上郡上毛町、築上郡築上町
佐賀県の対応エリア
- 市
- 佐賀市、鹿島市、伊万里市、鳥栖市、唐津市、神埼市、武雄市、多久市、嬉野市、小城市
- 町村
- 三養基郡基山町、三養基郡みやき町、三養基郡上峰町、藤津郡太良町、神埼郡吉野ヶ里町、西松浦郡有田町、東松浦郡玄海町、杵島郡白石町、杵島郡大町町、杵島郡江北町
長崎県の対応エリア
- 市
- 対馬市、長崎市、平戸市、島原市、雲仙市、諫早市、佐世保市、松浦市、南島原市、大村市、壱岐市、五島市、西海市
- 町村
- 東彼杵郡川棚町、東彼杵郡東彼杵町、東彼杵郡波佐見町、西彼杵郡時津町、西彼杵郡長与町、北松浦郡江迎町、北松浦郡小値賀町、北松浦郡佐々町、南松浦郡新上五島町
熊本県の対応エリア
- 市
- 熊本市内全域(南区、北区、東区、西区、中央区)、人吉市、阿蘇市、荒尾市、上天草市、八代市、玉名市、水俣市、菊池市、宇土市、山鹿市、合志市、宇城市、天草市
- 町村
- 下益城郡美里町、玉名郡長洲町、玉名郡南関町、玉名郡玉東町、玉名郡和水町、菊池郡菊陽町、菊池郡大津町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡高森町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡南阿蘇村、阿蘇郡西原村、上益城郡嘉島町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、上益城郡益城町、上益城郡御船町、天草郡苓北町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、八代郡氷川町、球磨郡多良木町、球磨郡錦町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡球磨村、球磨郡五木村、球磨郡相良村、球磨郡山江村、球磨郡あさぎり町
大分県の対応エリア
- 市
- 大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市
- 町村
- 東国東郡姫島村、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町、速見郡日出町
宮崎県の対応エリア
- 市
- 宮崎市、えびの市、串間市、延岡市、都城市、小林市、日向市、日南市、西都市
- 町村
- 西諸県郡高原町、東諸県郡綾町、東諸県郡国富町、北諸県郡三股町、児湯郡新富町、児湯郡高鍋町、児湯郡木城町、児湯郡都農町、児湯郡川南町、児湯郡西米良村、東臼杵郡諸塚村、東臼杵郡椎葉村、東臼杵郡門川町、東臼杵郡美郷町、西臼杵郡日之影町、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡五ヶ瀬町
鹿児島県の対応エリア
- 市
- 鹿児島市、南九州市、鹿屋市、指宿市、阿久根市、出水市、枕崎市、垂水市、西之表市、日置市、曽於市、姶良市、薩摩川内市、いちき串木野市、霧島市、志布志市、奄美市、南さつま市、伊佐市
- 町村
- 鹿児島郡三島村、鹿児島郡十島村、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、肝属郡錦江町、肝属郡南大隅町、肝属郡肝付町、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町、熊毛郡屋久島町、大島郡大和村、大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡喜界町、大島郡徳之島町、大島郡天城町、大島郡伊仙町、大島郡和泊町、大島郡知名町、大島郡与論町
沖縄県の対応エリア
- 市
- 那覇市、豊見城市、石垣市、宮古島市、宜野湾市、名護市、糸満市、浦添市、南城市、沖縄市、うるま市
- 町村
- 島尻郡与那原町、島尻郡八重瀬町、島尻郡南風原町、島尻郡伊是名村、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡渡名喜村、島尻郡南大東村、島尻郡粟国村、島尻郡北大東村、島尻郡伊平屋村、島尻郡座間味村、島尻郡久米島町、国頭郡大宜味村、国頭郡国頭村、国頭郡東村、国頭郡本部町、国頭郡恩納村、国頭郡金武町、国頭郡宜野座村、国頭郡今帰仁村、国頭郡伊江村、宮古郡多良間村、中頭郡西原町、中頭郡嘉手納町、中頭郡読谷村、中頭郡北中城村、中頭郡中城村、中頭郡北谷町、八重山郡与那国町、八重山郡竹富町