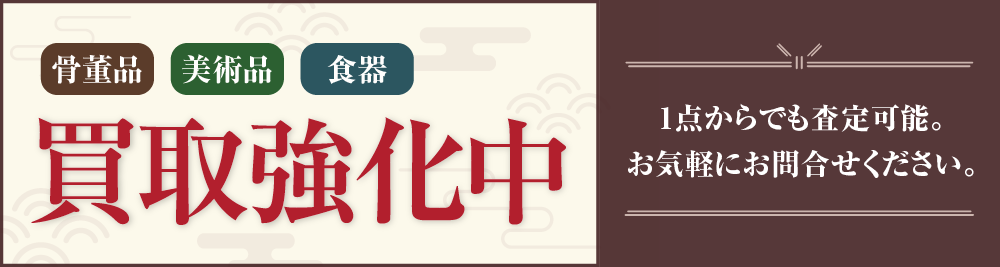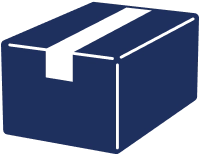初代肥前忠吉 日本刀の買取実績とお客様の声
査定士から聞いたお客様とのやりとりの一部を抜粋して記事にしております。
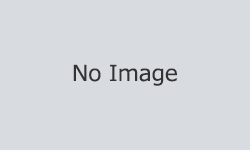
初代肥前忠吉 日本刀
福島県会津若松市にお住いのお客様より初代肥前忠吉作の日本刀をお買取りいたしました。肥前忠吉といえば最上大業物14工の内の一人です。そんな有名な初代肥前忠吉の刀ですが、やはり品質を維持した上での保存は難しいとのことでお売りいただきました。大変丁寧に手入れされていた様子が伺え、錆もなく立派なお品でした。そのため、しっかりと価格の提示もさせていただきましたが、喜んでいただけて何よりです。この度は日晃堂を利用していただきありがとうございました。
ご売却頂いたお客様の声
骨董品を集めるのが趣味で、刀剣を譲ってもらう機会があったため刀剣にも手を出したのですが、手入れ用の道具の購入や普段の手入れなど中々手間暇がかかってしまうためどうせならもっと刀剣が好きな人のところに行ってもらおうと思い日晃堂さんに買取のお願いをしました。元々日晃堂さんは利用したことがあったので安心してお任せできました。次も機会がありましたらよろしくお願いします。
- 初代肥前忠吉の歴史
- 刀鍛冶の名手として名高い肥前の刀鍛冶である忠吉は1572年(元亀3年)に高木瀬村長瀬(現在の佐賀県佐賀市)にて生まれました。忠吉は龍造寺家の家臣である橋本道弘の息子で本名を橋本新左衛門。橋本家は武士の家系で少弐氏の一族とされています。そのため、忠吉の祖父である盛弘と父の道弘は戦場に赴きますが沖田畷の戦いにて討死してしまいます。当時まだ13歳だった忠吉は軍役叶わず、刀匠に転身することとなりました。忠吉は1596年に上京をし、埋忠明寿の門をくぐり刀工としての道を歩み腕を磨きました。1598年になると忠吉は帰国し、佐賀城下町に居を構えました。戦功ある家柄として鍋島勝茂から改めて取り立てられることとなり、忠吉は代々藩の刀匠として栄える事になりました。
- 初代肥前忠吉の特徴
- 製作の時期によって、忠吉の刀の銘がかわります。「五字忠銘」「秀岸銘」「住人銘」忠吉から改名した後の「忠広」の銘に分かれます。忠吉の刀は均衡の取れた刀身が特徴的で、地鉄は米糠肌となっておりいかにも肥前刀らしい青黒く冴えた刃が魅力的な刀です。延寿や来國光に迫るような出来が忠吉の刀造りの目標でした。肥前刀の最大の魅力は何といってもどこをとっても無理がなく品が良くて美しいこと、そしてなによりよく斬れることです。また、銘がやや縦長になっているのは忠吉の中期頃の特徴で、初期の銘はそれとは逆で横に押し広がるようなものになっています。完成期の刀になると帽子の返りが浅く、これは初代の忠吉ならではの特徴の一つです。
刀剣の所持・買取には必ず
【銃砲刀剣類登録証】が必要となります
※未登録の刀剣以外にも査定ご希望のお品物があれば、ご相談ください。
買取についてのご相談・ご依頼はコチラ
丁寧に対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にお電話ください。
骨董品・古美術品の相談をする
0120-961-491
はじめての方でも安心して
ご利用いただけます
日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです
-
01
お問い合わせ
電話、LINE、メールで
らくらく
お申し込み。 -
02
査定
出張買取は全国どこでも。
店頭や宅配もお気軽に。 -
03
お支払い
即!その場で現金お手渡し。
※宅配買取は振込
ご都合に合わせて選べる
買取方法
システムメンテナンスのため、2025年12月12日(金)より新規の宅配買取受付を一時停止させていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。