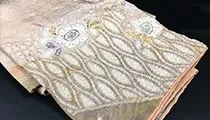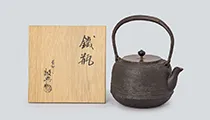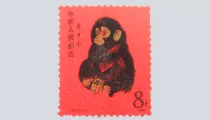森寛斎(もりかんさい)1814年–1894年

森寛斎は、江戸時代末期から明治中期にかけて活躍した日本画家です。
初めは円山応挙が築いた円山派の絵画を学び、丹念な写生を旨とする画風を会得。そのうえで、文人(教養人)の濃厚な詩情を盛り込む南画の影響を受け、円山派を超える新たな作風を打ち立てようと模索し、ついには“明治の応挙”と呼ばれるまでに至ります。その作品の多くは美術館・博物館に所蔵されており、いずれも高い価値を誇ります。
円山派を乗り越えて独自の境地に達した画家
1814年、森寛斎は江戸時代後期の長州藩(現在の山口県)に籍を置く藩士の子として生まれました。
本名は石田尚太郎。18歳のとき大阪にのぼり、画家・森徹山のもとで円山派の絵画を学び、26歳のとき森家の養子となり、森寛斎と名乗るようになります。
師匠の森徹山は、江戸時代中期に隆盛をきわめたものの、後期に至って衰退しつつあった円山派の再興を夢みていました。大阪にいたとき、若き寛斎に出会ってその才能を認め、養子にして夢を託します。 そんな徹山は、寛斎を養子とした翌年の1841年に死去。その後、寛斎は西日本を遍歴して絵画の学びを深め、やがて南画の技法を学ぶようになります。 「円山派の絵は写生を重視し過ぎたために飽きられたのだ」と考えた寛斎は、南画の技法を取り入れた詩情豊かな画風を打ち立てようと模索します。
一方、長州藩に縁があったということで、幕末の動乱期には勤王の志士たちと交わりを深め、自らも京都と長州を行き来する密使として活動します。 一時は、京都に設置された幕府の治安維持部隊・新選組に命を狙われたこともあったといわれています。
そんな寛斎ですが、明治以降は画家一筋の道を選びました。 展覧会に盛んに作品を発表し、「葡萄と栗鼠図」などの代表作を生み出します。 また1880年、京都府画学校が設立されたときには職員として勤め、講師として教鞭をとりました。 さらに1890年には帝室技芸員に任じられ、名実ともに日本画壇を代表する画家のひとりとなり、1894年に死去するまで悠々自適の後半生を送りました。
森寛斎の代表作
-
「葡萄と栗鼠図」
葡萄の枝に2匹の栗鼠(リス)が取りつき、見つめ合っている図を描いています。淡い三日月がかかる夜空はほんのり明らみ、幽玄な色合いを醸し出しています。 水墨の潤み、にじみを効果的に活用して、奥ゆきのある空間を創出する寛斎の代表作です。 この作品は展覧会に出品されて高い評価を受け、明治天皇に請われた寛斎はもう1枚、同じ題材で描いて献上したというエピソードが残されています。
-
「松林瀑布山水図」
激しく落ちる瀑布(滝)を中心に、松の木が茂る山水風景を描いた作品です。 冷たい水煙、滝壺で生き物のように自在にうねる水が繊細に表現され、轟々と山水を揺さぶる滝の音が聞こえてきそうな迫力に満ちています。 円山派の写実を超えた新たな表現を模索した寛斎の試みが、明らかに現れた作品です。
その他、「芥川図」「観瀑図屏風」などが代表作として知られています。

※30%UP対象商品:骨董品、美術品、食器
※査定時の買取価格に30%UPを上乗せして金額をご提示させていただきます。
※店頭買取・宅配買取は本キャンペーンの対象外となります。
※キャンペーンの併用は不可です。
買取についてのご相談・ご依頼はコチラ
丁寧に対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にお電話ください。
骨董品・古美術品の相談をする
0120-961-491
はじめての方でも安心して
ご利用いただけます
日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです
-
01
お問い合わせ
電話、LINE、メールで
らくらく
お申し込み。 -
02
査定
出張買取は全国どこでも。
店頭や宅配もお気軽に。 -
03
お支払い
即!その場で現金お手渡し。
※宅配買取は振込
ご都合に合わせて選べる
買取方法
他店で断られた状態不良の
お品物でも
お気軽にお問合せください
独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。
ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ
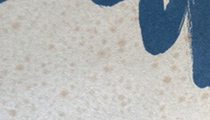
シミ

虫食い
骨董品・食器買取における対応エリア
日本全国どこからでもご利用いただけます。