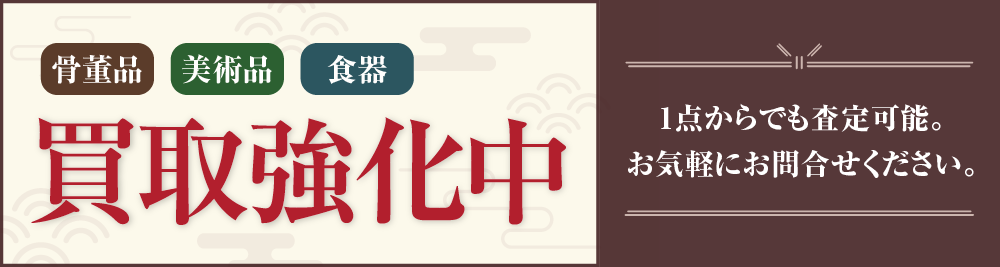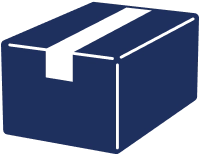大西浄元作鶴首釜の買取実績とお客様の声
査定士から聞いたお客様とのやりとりの一部を抜粋して記事にしております。

大西浄元作 鶴首釜
大西家といえば千家十職の釜師として有名です。室町時代の後期から400年以上続く歴史ある京釜師の家。今回は、六代目浄元作の鶴首釜をお買取りしました。少しの使用感は見受けられましたが、共箱もほとんど綺麗な状態で保存されていたため、お客様もご納得の買取金額にて買取させていただきました。大西家の茶釜ならぜひ日晃堂におまかせください。
ご売却頂いたお客様の声
当時コレクションとして骨董店から購入したものの特にどこかに飾るでもなく、倉庫の中に片したままでした。倉庫の掃除をしていた際に見つけ、埃を被ったままの状態で置いていても仕方ないという話になり売りに出すことに...。主人が人伝に聞いたという日晃堂さんにお願いしたのですが、しっかり説明して下さった上に満足のいく買取額を付けて頂いて大変満足しております。
- 大西浄元の歴史
- 六代目である大西浄元は、四代目浄頓の子にあたります。江戸時代中期の京都三条釜座の釡師で幼名は清吉、名は重義、通称を清右衛門、浄元を号とします。また、後の九代目である浄元とは区別をするために「古浄元」と言われています。六代目の浄元が活躍した時代は侘茶が定着し千家流の茶道は爛熟期に入りました。それにより侘茶に向いた茶釜が求められ、大西家も六代目の浄元の代から千家に出入りをするようになりました。
- 大西浄元の特徴
- 前述の通り、6代目浄元の時代は侘茶に向いた茶釜が求められるようになっていました。浄元は草庵風の茶に向くように独自地肌を持つ茶釜を作り始めるようになります。そうして釜の制作自体が増えていき、浄元の作家としての意識も高まっていきました。茶釜の制作をしていくにつれ、形も阿弥陀堂釜や鶴首釜などが多く作られ、焼き抜きの手法を使ったそれは細かい打肌で整った肌身を呈しました。そうして大西家風の作風が確立していったのです。浄元の作風はどちらかといえば茶釜の中では大まかで風雅な趣があり、上品な大人しい釜に分類されます。
- 鶴首釜について
- 6代目浄元といえば責紐釜や鶴首釜、雷声釜が有名です。その中から鶴首釜にフォーカスしてご紹介します。鶴首釜は茶釜の形状のひとつ。釜の口の造りがやや細長い形をしているのが特徴です。名の通りこの細長い部分を鶴の首に見立て、この名がつきました。鶴首釜には紹鴎好みや利休好みなどがあり、それぞれ鶴首釜の中でも少し形状が異なります。利休好みは小ぶりで鬼面鐶付、共蓋のものを指します。
買取についてのご相談・ご依頼はコチラ
丁寧に対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にお電話ください。
骨董品・古美術品の相談をする
0120-961-491
はじめての方でも安心して
ご利用いただけます
日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです
-
01
お問い合わせ
電話、LINE、メールで
らくらく
お申し込み。 -
02
査定
出張買取は全国どこでも。
店頭や宅配もお気軽に。 -
03
お支払い
即!その場で現金お手渡し。
※宅配買取は振込
ご都合に合わせて選べる
買取方法
システムメンテナンスのため、2025年12月12日(金)より新規の宅配買取受付を一時停止させていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。