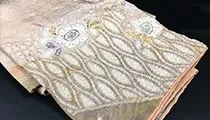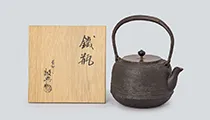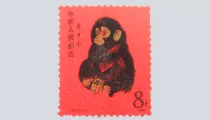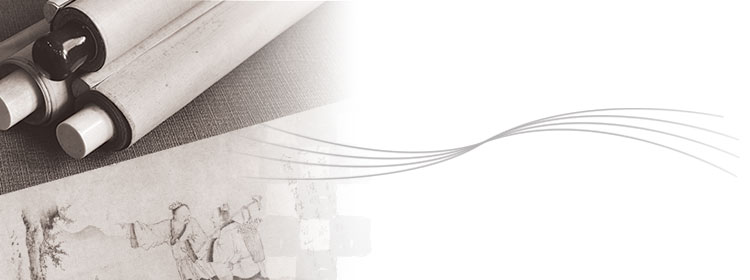
顔輝(がんき)生没年不詳

顔輝は、13世紀末の中国で活躍した画家です。
生没年は不詳ですが、南宋時代から元時代へと移り変わる1270年代の末に活躍したと考えられています。
古今の仙人や高僧たちの肖像画を専門とする「道釈人物画」を得意としており、半ば伝説として語られる人々の姿を人間くさくユーモラスに描くタッチが特徴として挙げられます。
顔かたちを誇張して描くクセのある肖像画は、怪奇趣味ともいうべき趣きを見せています。しかし決しておどろおどろしさはなく、どことなくおかしみのある魅力的な作品に仕上がっています。
そんな顔輝は、道釈人物画の分野において巨匠とされる画家であり、その作品は高い価値を持ちます。
仙人たちの姿を生き生きと描いた宋末元初の画家
生年不詳の顔輝が歴史の表舞台に登場したのは、南宋時代の末期(1270年代後半)のこと。
山水画や人物画において並々ならぬ才能を見せており、当時の文化人たちの間で大いにもてはやされたと伝えられています。特に人物画には、突出した才能を持っていました。
1290年代末から1300年代の初めには、現在の中国江西省にいたのではないかと考えられています。 当時、水害で被害を受けた道教寺院が修復される際、壁画を制作して評判をとったという伝承が残っています。またこの頃は、元王朝の宮廷画家として活躍していたのではないかという説もあります。
そんな顔輝は、自然の風物を題材にとった作品に定評があるといわれていましたが、いつの頃からか道教や仏教、儒教の世界で伝説として伝わる人物たちの絵画を得意とするようになっていきます。 そのような絵画を「道釈人物画」と呼びますが、顔輝はその分野において第一人者と目されています。
顔輝の代表作
-
「蝦蟇鉄拐図」
劉海蟾(りゅうかいせん)、李鉄拐(りてっかい)というふたりの仙人をそれぞれ描いた作品です。
海蟾が“ガマ仙人”というあだ名で呼ばれていたことが、タイトルの由来です。 ガマガエルを背負って不敵な微笑みを浮かべるガマ仙人と、ごつごつの顔かたちをこわばらせて体を硬直させている死に瀕した李鉄拐の姿が描かれています。あぶらが乗り切っていた頃に描かれた作品といわれており、仙人たちの表情や体の動きが手に取るようです。 日本でも人気が高い作品で、現在は京都の知恩院に所蔵されています。 -
「寒山拾得図」
唐の時代に活躍した狂僧・寒山(かんざん)と拾得(じっとく)を題材とする作品です。 寒山、拾得はいつでもふたり一緒で遊びまわっていたという逸話を持つ僧たちで、この作品では不気味なほど無邪気に笑うその姿が生き生きと活写されています。 こちらは現在、東京国立博物館に所蔵されています。
その他、「羅漢図」「波濤図」などが代表作として知られています。

※30%UP対象商品:骨董品、美術品、食器
※査定時の買取価格に30%UPを上乗せして金額をご提示させていただきます。
※店頭買取・宅配買取は本キャンペーンの対象外となります。
※キャンペーンの併用は不可です。
買取についてのご相談・ご依頼はコチラ
丁寧に対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にお電話ください。
骨董品・古美術品の相談をする
0120-961-491
はじめての方でも安心して
ご利用いただけます
日晃堂で骨董品・古美術品を売るのはとてもカンタンです
-
01
お問い合わせ
電話、LINE、メールで
らくらく
お申し込み。 -
02
査定
出張買取は全国どこでも。
店頭や宅配もお気軽に。 -
03
お支払い
即!その場で現金お手渡し。
※宅配買取は振込
ご都合に合わせて選べる
買取方法
他店で断られた状態不良の
お品物でも
お気軽にお問合せください
独自の販売ルートを確立している日晃堂なら、以下のようなお品物でも、しっかりと査定することが可能です。
ご売却をご検討中の古美術品・骨董品がございましたら、査定は完全無料ですので、お気軽にお問合せください。

欠け

汚れ

変形

サビ
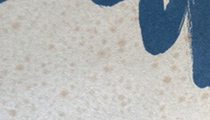
シミ

虫食い
骨董品・食器買取における対応エリア
日本全国どこからでもご利用いただけます。